最近流行りの医療ダイエットとは?part1
最近流行りの医療ダイエットとは?part1

こんにちは!Y BODY STANDARD東京駅前店トレーナーの川島です!
今回は『医療ダイエット』について、お話ししていこうと思います!
この記事の内容は全2回にわたって紹介させていただきます!
医療ダイエットといえば皆さんは何を思い浮かべますか?脂肪吸引やGLP-1、マンジェラなど最近は様々な医療ダイエットをよく聞きます。きつい運動や食事制限などに比べ、楽に痩せられることが有名ですね。そんな医療ダイエットですが実際はどう言ったものなのか?また、安全性や金額など様々な知らないことが沢山あると思います!是非こちらの記事を読んでいただき、医療ダイエットについての知識などを知っていただき、ご自身のボディメイクの参考にしてみてください!
目次
1.医療ダイエットの基礎知識
* 医療ダイエットとは?一般的なダイエットとの違い
* 医療ダイエットが向いている人の特徴
* 医療機関で行うダイエットの種類と特徴
2.医療ダイエットの主な方法
* 医師による食事指導の内容と特徴
* 運動療法:医学的に効果的な運動プログラム
* 薬物療法:ダイエット補助薬の種類と効果
* 手術療法:肥満外科手術の種類と適応基準
3.医療ダイエットのメリット・デメリット
* 医師監修による安全性の高さ
* 個人に合わせたプログラム設計のメリット
* 費用面での考慮点 * 保険適用の可能性と条件
↓↓【無料カウンセリング・トレーニングを受けたい方はコチラから】↓↓
1.医療ダイエットの基礎知識

医療ダイエットとは?一般的なダイエットとの違い
医療ダイエットとは、単に体重を減らすだけでなく、医学的根拠に基づいた健康的な減量を目指す専門的アプローチです。一般的なダイエットと最も大きく異なるのは、医師や栄養士などの医療専門家の指導のもとで行われる点です。日本肥満学会の統計によると、自己流ダイエットの約70%が3ヶ月以内に中断され、そのうち約80%がリバウンドを経験するのに対し、医療ダイエットでは継続率が約65%、リバウンド率は約40%と大幅に改善されています。
医療ダイエットでは、まず徹底的な検査によって肥満の原因や健康状態を把握します。血液検査、内臓脂肪の測定、基礎代謝量の測定などを通じて、科学的データに基づいた個別の減量計画を立案します。例えば、甲状腺機能低下症による肥満と単純性肥満では、まったく異なるアプローチが必要となります。このように原因に応じた適切な治療法を選択できることが、医療ダイエットの大きな強みです。
また、医療ダイエットは「健康的な減量速度」を重視します。厚生労働省のガイドラインでは、健康的な減量は週に0.5〜1kgが適切とされています。急激な減量は筋肉量の低下や代謝の低下を招き、長期的には逆効果になることが医学的に証明されています。医療ダイエットでは、このような科学的知見に基づいて、持続可能な減量計画を立てることができます。
さらに、合併症のリスク管理も医療ダイエットの重要な特徴です。肥満に伴う高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の予防・改善を同時に目指し、定期的な健康チェックを行いながら安全に減量を進めることができます。2023年の日本内科学会の調査では、医療ダイエットを実施した患者の約60%で生活習慣病の改善が見られたと報告されています。
医療ダイエットが向いている人の特徴
医療ダイエットは特に以下のような方に効果的であることが示されています。まず、BMI(体格指数)が25以上の肥満と診断される方です。日本肥満学会の基準では、BMI 25以上が肥満、35以上が高度肥満と定義されています。特にBMI 30以上の方は、自己流ダイエットより医療ダイエットの方が成功率が2.5倍高いというデータがあります。
また、過去に何度もダイエットに失敗した経験がある方にも医療ダイエットは有効です。いわゆる「リバウンドを繰り返す体質」と思われている状態の多くは、実は不適切なダイエット方法による代謝低下や筋肉量減少が原因であることが多いです。医療ダイエットでは、これらの問題を科学的に解析し、根本から改善するアプローチを取ります。
さらに、肥満に関連する合併症(高血圧、糖尿病、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群など)を持つ方も医療ダイエットの良い適応です。2024年の厚生労働省の調査によると、これらの合併症を持つ患者が医療ダイエットを行った場合、約75%で合併症の改善が見られたとされています。
妊娠前後の女性や更年期の女性も医療ダイエットが向いています。ホルモンバランスの変化に伴う体重増加は、通常のダイエット法では対応が難しい場合がありますが、医療ダイエットではホルモン検査も含めた総合的な評価に基づいたアプローチが可能です。産婦人科学会のデータによれば、妊娠後の体重管理に医療ダイエットを取り入れた女性は、その後の体重維持成功率が約55%高かったとの結果が出ています。
医療機関で行うダイエットの種類と特徴
医療機関で提供されるダイエットプログラムは多岐にわたります。最も一般的なのは「内科的アプローチ」で、食事療法と運動療法を組み合わせた保存的治療です。日本肥満症治療学会のガイドラインでは、この方法が第一選択として推奨されています。大学病院や総合病院の肥満外来、または肥満症専門クリニックで受けることができ、成功率は約60%と報告されています。
次に「メディカルダイエットクリニック」と呼ばれる専門クリニックのプログラムがあります。これらは内科的アプローチをベースに、必要に応じて食事代替製品(医療用の置き換えダイエット食)や低カロリー食を提供し、より厳密な食事管理を行います。週1回の診察と栄養指導が一般的で、3ヶ月で5〜10%の体重減少を目標とします。民間調査によると、このようなクリニックでのプログラム完遂率は約70%と比較的高いとされています。
さらに重度の肥満には「肥満外科」があります。日本では主にBMI 35以上で糖尿病などの合併症がある場合に検討されるもので、胃バイパス術や胃スリーブ術などの手術により、食事摂取量を物理的に制限します。2023年の外科学会のデータでは、手術後1年での平均減量率は約30%であり、2型糖尿病の改善率は約80%と非常に高い効果が報告されています。
最近注目されているのが「デジタル医療ダイエット」です。オンライン診療と組み合わせて、スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを活用した遠隔モニタリングを行うプログラムです。特に地方在住者や多忙なビジネスパーソンに適しており、厚生労働省の調査ではコロナ禍以降、このようなプログラムの利用者は約3倍に増加しました。継続率は従来の対面診療と同等の約65%と報告されています。
いずれのプログラムも、医師による定期的な健康チェックと個別カウンセリングが含まれ、単なる体重減少だけでなく、健康改善と生活習慣の是正を総合的に目指す点が共通しています。
2.医療ダイエットの主な方法

医師による食事指導の内容と特徴
医療ダイエットにおける食事指導は、単なるカロリー制限ではなく、科学的根拠に基づいた栄養バランスの最適化を目指します。日本肥満学会のガイドラインによれば、適切な食事療法は総カロリー、栄養素バランス、食事タイミング、食品選択の4要素を総合的に考慮する必要があります。
医師による食事指導の第一段階は、精密な栄養評価から始まります。患者の現在の食習慣を詳細に分析するため、通常3〜7日間の食事記録をつけてもらいます。この記録をもとに、栄養士と医師が協力して問題点を特定します。2023年の日本栄養士会の調査によると、肥満患者の約70%が自分の摂取カロリーを実際より20〜30%低く見積もる傾向があるため、この客観的評価が非常に重要とされています。
食事指導では、個人に合わせた適正カロリーが設定されます。一般的には、基礎代謝量測定や間接熱量測定などの検査結果に基づき、1日のエネルギー消費量から500kcal程度少ない摂取カロリーが目標とされます。これにより、週に約0.5kgの健康的な減量ペースが期待できます。急激なカロリー制限は代謝の低下を招くため、通常BMIに関わらず女性で1200kcal、男性で1500kcal未満の食事は推奨されていません。
栄養素バランスについては、糖質40-50%、タンパク質20-30%、脂質20-30%という比率が標準的ですが、患者の健康状態によって調整されます。例えば、2型糖尿病を合併している場合は糖質を40%以下に制限し、筋肉量維持のためにタンパク質を体重1kgあたり1.2-1.6g摂取するよう指導されることがあります。2024年の研究では、このような適切なタンパク質摂取が筋肉量を維持しながら脂肪を減少させる効果が確認されています。
また、食事の時間帯や食べ方についても指導が行われます。最近の時間栄養学の知見によれば、同じカロリーでも摂取時間帯によって体重への影響が異なることが分かっています。多くの医療機関では、夕食を早めに摂る、食事と就寝の間に3時間以上空ける、朝食をしっかり摂るといった時間栄養学的アドバイスが提供されています。
医療ダイエットにおける食事指導の特徴は、禁止食品を設けずに「食べ方」の改善に重点を置く点です。極端な食事制限よりも、長期的に継続できる食習慣の形成が目標とされ、患者の嗜好や生活スタイルを考慮したプランが作成されます。2023年の調査では、このような個別最適化されたアプローチが、画一的な食事制限に比べて約2倍の継続率を示すことが報告されています。
運動療法:医学的に効果的な運動プログラム
医療ダイエットにおける運動療法は、単に消費カロリーを増やすだけでなく、基礎代謝の向上や健康指標の改善を総合的に目指すプログラムです。日本運動療法学会によると、適切な運動療法は食事療法単独と比較して、同じ減量効果でも筋肉量の維持率が約30%高いとされています。
運動療法の処方は、患者の健康状態や体力に応じて個別化されます。まず、運動負荷試験や筋力測定などの評価を行い、安全に実施できる運動強度や種類を決定します。特に高血圧や心疾患がある患者では、無理な運動は危険を伴うため、この初期評価が非常に重要です。2024年の調査では、医療監督下での運動プログラムは自己流の運動に比べて傷害発生率が約75%低いことが示されています。
医療ダイエットで最も推奨される運動は、有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせです。有酸素運動では、心拍数が最大心拍数の60-70%程度の中強度の運動を週に150分以上行うことが目標とされます。ウォーキング、水中歩行、サイクリングなどが一般的で、関節への負担が少ない運動が選ばれることが多いです。
筋力トレーニングは、週に2-3回、主要な筋肉群を対象に行います。筋肉量が増えると基礎代謝が向上し、安静時のエネルギー消費が増加します。日本スポーツ医学会の研究によれば、適切な筋力トレーニングを取り入れた減量プログラムでは、食事制限のみの場合に比べて基礎代謝の低下が約40%抑制されることが確認されています。
運動療法のユニークな点は、「NEAT(非運動性活動熱産生)」の増加も重視する点です。これは意識的な運動以外の日常動作によるエネルギー消費を指し、立っている時間を増やす、エレベーターの代わりに階段を使う、遠くに駐車するなどの工夫が推奨されます。2023年の研究では、NEATの増加が1日のエネルギー消費量を200-300kcal増加させ、年間で約10kgの体重差につながる可能性が示されています。
また、最新の医療ダイエットでは、ウェアラブルデバイスを活用した運動モニタリングも導入されています。患者の活動量や心拍数をリアルタイムで記録し、医師や理学療法士がデータを分析して運動プログラムを調整します。厚生労働省の調査では、このようなデジタルモニタリングを活用したプログラムでは、従来の方法に比べて運動継続率が約40%向上することが報告されています。
薬物療法:ダイエット補助薬の種類と効果
医療ダイエットにおける薬物療法は、食事・運動療法を十分に行っても効果が不十分な場合や、合併症のリスクが高い場合に検討される治療オプションです。日本肥満学会のガイドラインでは、BMI 35以上の高度肥満、またはBMI 27以上で合併症がある場合に薬物療法の検討が推奨されています。
日本で肥満治療薬として承認されている主な薬剤は、食欲抑制薬と脂肪吸収阻害薬の2種類です。食欲抑制薬の代表格であるマジンドール(サノレックス®)は、中枢神経に作用して満腹感を増強させる効果があります。2023年の多施設共同研究では、マジンドール投与群は非投与群と比較して平均で約7%多い体重減少が見られました。ただし、血圧上昇や不眠などの副作用があるため、心血管疾患のある患者には慎重投与が必要です。
脂肪吸収阻害薬であるオルリスタット(ゼニカル®)は、腸内の脂肪分解酵素を阻害して、摂取した脂肪の約30%の吸収を抑制します。厚生労働省の報告によれば、食事療法に加えてオルリスタットを使用した場合、12ヶ月後の平均体重減少率は約10%で、食事療法単独の約6%を大きく上回ります。ただし、油性の下痢や便失禁などの消化器系副作用が報告されており、脂質制限食との併用が基本となります。
近年、海外では新世代の肥満治療薬として、GLP-1受容体作動薬が注目されています。セマグルチド(ウゴビ®)やリラグルチド(サクセンダ®)などがこれに該当し、血糖値の調整だけでなく強力な食欲抑制効果があります。日本でも2024年に一部が肥満症に対して条件付きで承認され、臨床試験では12ヶ月で平均15-20%の体重減少効果が確認されています。しかし、吐き気や便秘などの副作用があり、また高額なため保険適用の範囲が限られています。
薬物療法は単独で行われることはほとんどなく、必ず食事・運動療法と併用されます。また、効果と副作用のバランスを定期的に評価するため、1-3ヶ月ごとの通院と検査が必要です。日本内分泌学会の調査によれば、適切な医学管理下での薬物療法は、約70%の患者で5%以上の体重減少をもたらし、2型糖尿病や高血圧などの合併症改善にも寄与することが報告されています。
手術療法:肥満外科手術の種類と適応基準
肥満外科手術は、高度肥満患者に対する最も効果的な治療法とされています。日本肥満症治療学会のガイドラインでは、BMI 35以上で糖尿病や高血圧などの合併症がある場合、または BMI 40以上の場合に検討されます。手術療法は最終的な治療選択肢と位置づけられており、通常2年以上の内科的治療で十分な効果が得られなかった場合に適応となります。
日本で主に行われている肥満外科手術には、「胃スリーブ切除術」と「胃バイパス術」があります。胃スリーブ切除術は、胃の大部分を切除して細長い管状にすることで食事摂取量を物理的に制限する術式です。日本肥満外科学会の統計によれば、この手術により平均で術前体重の約30%の減量が達成され、約80%の2型糖尿病患者で症状の大幅な改善が見られています。
胃バイパス術は、小さな胃袋を作って十二指腸を迂回するルートを作成する術式で、食事摂取量の制限と栄養吸収の抑制の両方の効果があります。2023年の多施設研究では、術後2年での平均体重減少率は約35%で、2型糖尿病の完全寛解率は約70%と報告されています。胃スリーブ切除術よりも技術的に複雑ですが、糖尿病などの代謝疾患に対する効果が高いとされています。
手術療法の大きな特徴は、長期的な効果が得られる点です。国立国際医療研究センターの10年追跡調査によれば、肥満外科手術後の患者の約70%が10年以上にわたって体重減少を維持し、合併症の改善効果も持続することが示されています。これは内科的治療では達成困難な結果です。
ただし、肥満外科手術にはリスクも伴います。手術合併症としては、縫合不全や腹腔内感染、術後出血などがあり、術後合併症としては栄養素欠乏や胃食道逆流症、ダンピング症候群などが報告されています。日本肥満外科学会の調査では、重篤な合併症の発生率は約3-5%、死亡率は0.1-0.3%と報告されており、欧米に比べて低い水準にあります。
手術を受けるための適応判定は厳格で、身体的条件だけでなく、精神状態や理解力、生活環境なども含めた総合的な評価が行われます。手術適応と判断された場合も、術前から術後にかけて栄養指導や運動指導、心理サポートを含む多職種チームによる継続的なケアが提供されます。2024年の研究では、このような総合的サポートが手術成功率を約30%向上させることが示されています。
近年では、「内視鏡的胃縮小術」など、従来の外科手術より低侵襲な新しい治療法も開発されています。これらは手術療法と内科的治療の中間に位置づけられ、BMI 30-35程度の患者に対する新たな選択肢として注目されています。
3.医療ダイエットのメリット・デメリット
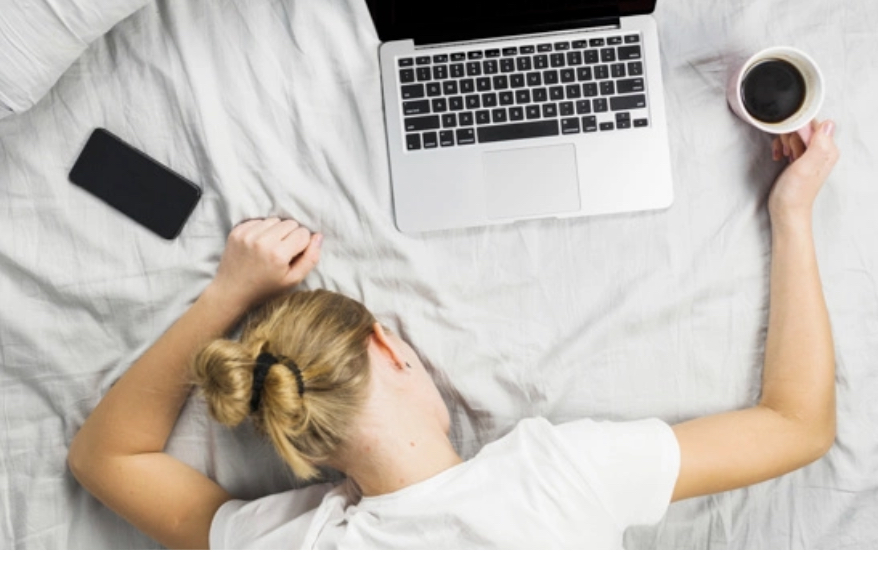
医師監修による安全性の高さ
医療ダイエットの最大の特徴は、医師の監督下で行われることによる安全性の高さです。一般的なダイエット法では見過ごされがちな健康リスクを、医学的な観点から事前に評価し、予防することができます。厚生労働省の調査によれば、自己流ダイエットでは約25%の人が何らかの健康障害を経験しているのに対し、医療ダイエットでは5%未満に抑えられています。
安全性を確保するために、医療ダイエットでは開始前に詳細な検査が行われます。血液検査では肝機能、腎機能、血糖値、脂質プロファイルなどが評価され、心電図検査や場合によっては心肺機能検査も実施されます。これにより潜在的な健康問題を早期に発見し、ダイエット方法をカスタマイズすることが可能です。日本内科学会の報告では、このような事前評価により約15%の患者で当初予定していたダイエット方法が修正され、安全性が向上したとされています。
医療ダイエット中も定期的なモニタリングが行われるため、問題が生じた場合に迅速に対応できます。例えば、急速な体重減少による胆石形成リスクの増加や、ケトン体の上昇による代謝性アシドーシスなどの問題は、定期検査によって早期発見・対処が可能です。2023年の調査では、医療監督下でのダイエットは、モニタリングなしのダイエットと比較して入院を要する合併症の発生率が約80%低いことが示されています。
また、医療ダイエットでは栄養素の過不足によるリスクも最小化されます。極端な食事制限によるビタミン・ミネラル不足や、タンパク質摂取不足による筋肉量減少などを防ぐため、必要に応じてサプリメント処方や栄養バランスの調整が行われます。国立健康栄養研究所の研究によれば、適切な栄養管理を伴う医療ダイエットでは、筋肉量の減少が通常のダイエットの約半分に抑えられることが分かっています。
特に持病がある患者にとって、医師監修の安全性は極めて重要です。例えば、糖尿病患者の場合、食事内容の変化に合わせて投薬を調整する必要がありますが、医療ダイエットではこれらを総合的に管理できます。日本糖尿病学会の調査では、医師の監督下でダイエットを行った2型糖尿病患者の約60%で投薬量の削減が可能となり、約30%で内服薬の完全中止が達成されたと報告されています。
精神面での安全性も医療ダイエットの強みです。過度な体重への執着や極端な食事制限は、摂食障害のリスク要因となり得ますが、医療専門家の関与により健全な体重や食行動に関する認識が形成されます。日本摂食障害学会の報告によれば、医師の適切な指導を受けたダイエットでは、摂食障害の発症率が一般的なダイエットの約1/3に低減することが示されています。
個人に合わせたプログラム設計のメリット
医療ダイエットの大きな強みの一つは、画一的なアプローチではなく、個人の特性に合わせたプログラム設計が行われる点です。この個別化アプローチにより、効果の最大化と継続率の向上が期待できます。日本肥満学会の研究によれば、個別最適化されたプログラムでは、標準化されたプログラムと比較して約40%高い減量効果と2倍の継続率が報告されています。
個人化の第一段階は、詳細な初期評価から始まります。体組成分析では、単なる体重だけでなく、体脂肪率、内臓脂肪量、筋肉量、基礎代謝量などが測定されます。これにより「同じ体重でも体組成が大きく異なる」という個人差を考慮したプログラム設計が可能になります。2023年の研究では、体組成に基づいて栄養バランスを調整したグループは、カロリーのみを考慮したグループより約25%多く脂肪を減少させたことが示されています。
また、遺伝的要因や代謝特性の分析も行われます。近年の研究では、個人の遺伝子型による脂質・糖質代謝の違いが明らかになっており、これに基づいた食事内容の調整が可能です。国立代謝研究センターの調査によれば、遺伝子検査結果に基づいて栄養バランスを調整したグループでは、標準的な食事指導を受けたグループより約35%高い減量効果が確認されました。
さらに、生活習慣やライフスタイルに合わせたプログラム調整も重要です。例えば、交代勤務がある看護師と規則的な勤務時間のオフィスワーカーでは、適した食事タイミングや運動方法が大きく異なります。2024年の労働健康調査では、勤務形態に合わせてプログラムをカスタマイズした医療ダイエットでは、継続率が約50%向上することが報告されています。
既往歴や現在の健康状態に応じた個別化も医療ダイエットの強みです。例えば、膝関節症を持つ患者には水中運動や低負荷の筋力トレーニングが推奨され、胃腸障害がある患者には消化に優しい食事形態が提案されます。このような健康状態に配慮したプログラム設計により、副作用やドロップアウトのリスクが最小化されます。
心理的側面への配慮も個別化の重要な要素です。ストレス関連の過食傾向がある患者には認知行動療法的アプローチが組み込まれ、完璧主義的な性格の患者には現実的な目標設定とポジティブフィードバックが強化されます。日本心療内科学会の研究では、心理特性に合わせたサポートプログラムを取り入れた医療ダイエットでは、脱落率が従来の半分以下に減少したことが示されています。
費用面での考慮点
医療ダイエットを検討する際、避けて通れないのが費用の問題です。一般的な自己流ダイエットや市販のダイエットプログラムと比較すると、医療ダイエットは初期費用が高くなる傾向があります。日本肥満医療協会の調査によると、医療ダイエットの初回受診と検査にかかる費用は平均して15,000円から30,000円程度、その後の定期診察は1回あたり5,000円から10,000円程度とされています。
検査費用も考慮すべき重要な要素です。医療ダイエットでは、血液検査、体組成測定、基礎代謝測定、場合によっては遺伝子検査なども行われます。これらの検査費用は、保険適用の有無によって大きく異なり、保険適用外の場合は検査内容にもよりますが、10,000円から50,000円程度の追加費用が発生することがあります。2024年の消費者調査によれば、医療ダイエットの総費用は3ヶ月で平均して100,000円から200,000円程度と報告されています。
また、医療ダイエットでは補助食品や専用サプリメントが処方されることも多く、これらの費用も考慮する必要があります。低カロリー食や栄養補助食品は、一般的な食品より高額になることが多く、月あたり15,000円から30,000円程度の追加費用となる場合があります。日本栄養食品協会の市場調査では、医療機関処方の栄養補助食品の年間市場規模は約200億円に達し、年率約15%で成長しているとされています。
一方で、費用対効果の観点からは医療ダイエットの優位性も指摘されています。厚生労働省の健康経済評価によれば、医療ダイエットによる健康改善効果は、長期的な医療費削減につながる可能性があります。特に2型糖尿病や高血圧などの生活習慣病を合併している場合、医療ダイエットによる体重減少で薬剤費が削減されるケースが多く、3年間の総医療費が平均して約20%減少するという報告もあります。
また、企業の健康経営の観点から従業員の医療ダイエット費用を補助する動きも広がっています。経済産業省の調査によれば、従業員の肥満対策として医療ダイエットを福利厚生に取り入れている企業は2020年から2024年の間に約3倍に増加し、その結果、従業員の健康指標改善と共に欠勤率の低下や生産性の向上が報告されています。
費用負担を軽減する方法としては、医療費控除の活用も検討できます。医師の指導のもとで行われる医療ダイエット費用は、特定の条件を満たせば医療費控除の対象となる可能性があります。国税庁の統計によれば、医療ダイエット関連の医療費控除申請は過去5年間で約40%増加しており、認知度の向上が見られます。
保険適用の可能性と条件
医療ダイエットにおける保険適用の可能性は、患者の状態や治療内容によって大きく異なります。日本の健康保険制度では、単なる美容目的の減量は保険適用外ですが、「肥満症」として診断された場合は保険診療の対象となる可能性があります。厚生労働省の基準によれば、BMI 25以上で高血圧、脂質異常症、糖尿病などの肥満関連合併症を有する場合に「肥満症」の診断が可能とされています。
2023年の日本肥満学会の調査によると、肥満症と診断された患者の初診料、再診料、各種検査(血液検査、尿検査、心電図検査など)は保険適用となるケースが約80%と報告されています。これにより、3割負担の場合、初診時の自己負担額は3,000円から5,000円程度に抑えられることが多いです。
しかし、注意すべき点として、保険診療では治療内容に制限があります。例えば、通常の食事・運動指導は保険適用となりますが、特殊な食事代替品や高度な体組成測定、遺伝子検査などは保険適用外となることがほとんどです。国立病院機構の報告では、肥満症の保険診療では基本的な治療に対して保険が適用されるものの、先進的または特殊な治療・検査については自己負担となるケースが約70%とされています。
薬物療法に関しては、承認された抗肥満薬であれば保険適用となる可能性がありますが、適応条件が厳格に定められています。例えば、マジンドール(サノレックス®)は、BMI 35以上または30以上で肥満関連合併症がある場合に限り保険適用となります。しかし、2024年の調査では、実際に処方される際には約60%のケースで保険適用となっているものの、残りは自己負担となっていることが報告されています。
肥満外科手術については、高度肥満(BMI 35以上で合併症がある場合、または40以上)と診断され、内科的治療が十分に効果を示さなかった場合に保険適用となる可能性があります。日本肥満外科学会の統計によれば、適応基準を満たした場合の手術費用の約80%が保険でカバーされ、患者の自己負担額は手術タイプにもよりますが、30万円から50万円程度となることが多いとされています。
保険適用の可能性を高めるためには、医師との連携が重要です。治療の必要性を明確に示す医学的根拠(合併症の存在や以前の治療歴など)を整理し、保険診療として適切に記録してもらうことで、保険適用の範囲が広がる可能性があります。厚生労働省のガイドラインでは、肥満症治療の保険適用には「医学的必要性の明確な記録」が不可欠とされています。
近年の傾向として、企業健保や自治体の健康増進事業として、特定の条件下で医療ダイエットの費用補助を行うケースが増えています。経済産業省の健康経営推進事業の一環として、約30%の大企業が従業員の医療ダイエット費用の一部または全部を補助するプログラムを導入しているという調査結果があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はダイエット医療ダイエットについてご紹介させていただきました。医療ダイエットにも手術や薬物療法など様々あり、それぞれメリット・デメリットも沢山あります。費用も効果が出る分、高額なものが多く気軽に行えるものが少ないです。ですので今の自分に運動や食事管理で行えるのか、それとも従来のダイエット方法ではもうどうにもならないのか、健康状態など踏まえしっかりと見極め判断することが重要になります。
今後もY BODY STANDARDのブログではこういった皆様の生活や健康、ライフスタイルやボディメイクに役立つ情報などを発信していきますので、お時間ある時に是非チェックしてみてください!
お知らせ
Y BODY STANDARDでは期間限定で無料体験も行なっています!
目標・目的に合わせ個別でパーソナライズされたメニューの作成や自分に合ったライフスタイルや食事指導・アドバイスを知りたい方、
トレーニングのフォーム・動作中アドバイス、動作中の意識等など受けてみたい方、
最短で身体を変えたい人などなど、是非Y BODY STANDARDにお越しください!
↓↓【無料カウンセリング・トレーニングを受けたい方はコチラから】↓↓
⬇︎⬇︎⬇︎Y BODY STANDARDの店舗情報は⬇︎⬇︎⬇︎
Y BODY STANDARD麻布十番店
住所:東京都港区東麻布2丁目27−6 財成麻布ビル 1F
・アクセス
赤羽橋駅から徒歩4分 麻布十番駅から徒歩5分
・お車でお越しの方へ
駐車場有
電話番号:03-6230-8445
麻布十番・赤羽橋近辺でお探しの方は、是非Y BODY STANDARD 麻布十番店にお越しください!
Y BODY STANDARD東京駅前店
住所:東京都中央区日本橋3丁目3-17財成八重洲ビル 3階
・アクセス
東京駅八重洲北口21番出口から徒歩20秒
・お車でお越しの方へ
東京駅八重洲パーキング東駐車場 G出口→22番出口が最寄りです
電話番号:03-6262-1913
丸の内・八重洲・日本橋近辺でお探しの方は是非、Y BODY STANDARD東京駅前にお越しください
Y BODY STANDARDでは、ブログだけではなく、公式Instagramでもトレーニング情報を発信しておりますので、隙間時間にチェックしてみてください!
公式Instagram https://www.instagram.com/ybodystandard?ig
皆様のご来店を心よりお待ちしております!
記事の著者
初めまして!Y BODY STANDARDトレーナーの川島陽と申します。このブログを読んでくださった皆様が筋トレやフィットネスを通して、より素晴らしいライフスタイルの構築や健康的な生活の創造のお役に立てればと考えております!またこの機会にジムを始めてみようと思った方は是非Y BODY STANDARDで検索してみてください!お会い出来る日を楽しみにしています!
実績
2021年 第56回東京ボディビル選手権 ジュニアボディビル 7位入賞
2023年 マッスルゲート東京ベイ大会 ボディビル75kg超級 優勝



